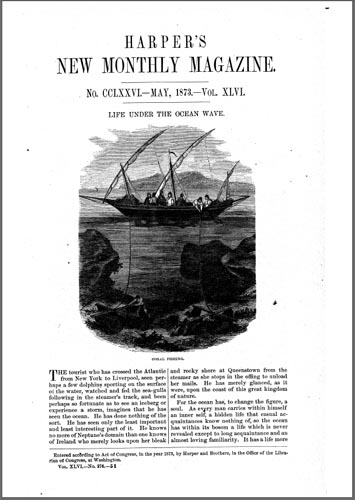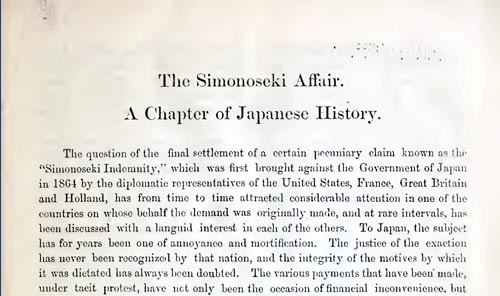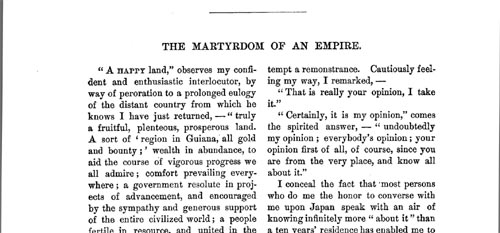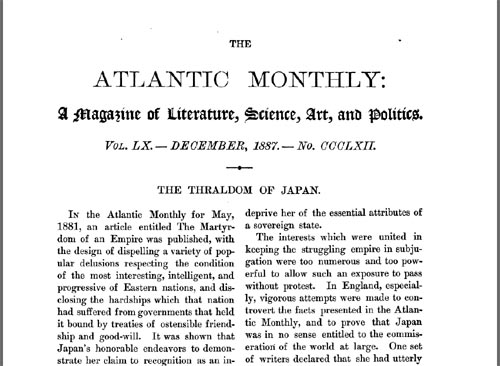19、特派員、エドワード・H・ハウス (その3)
チャールス・リゼンドルの政府新聞発行の建策と、エドワード・ハウスの『東京タイムス』紙の創刊
♦ チャールス・リゼンドルと大隈重信
アメリカのアモイ領事だったチャールス・W・リゼンドルが、明治5(1872)年の暮れ、当時の外務卿・副島種臣の要請に応え、外務省顧問として明治政府に雇われた事情は前章に書いた通りだ。そして当時の明治7(1874)年に起こった、明治政府の台湾生蕃討伐すなわち 「台湾蕃地処分出兵」に大きな影響を与え、その中心の1人として蕃地事務局の準二等出仕に任じられ、蕃地事務局長官・大隈重信や事務都督・西郷従道の補佐をした事も前章の通りだ。リゼンドルはこんな関係を基にし、明治6(1873)年10月に就任して以来の参議兼大蔵卿として、地租改正や殖産興業政策を通じ、国家の財政運営とその改革に取り組んだ大隈重信に様々な建策をしている。
当然台湾出兵に関するリゼンドルの建策や報告は数多くにのぼるが、その他に、日本の採るべき外交政策、日本国内の開発、華士族の活用、また政治システムに至るまで、多岐に渡っている事実は意外に知られていないように思われる。そんな中の一つに、ここで取り上げたい 「政府新聞発行」に関する大隈への建策がある。そしてその後、これがエドワード・ハウスの推薦につながり、ハウスの「東京タイムス」発行につながるのだ。
♦ チャールス・リゼンドルの政府新聞発行の建策
前章の記述の如く、アメリカ公使・ビンガムから蕃地事務局顧問・リゼンドルへの「渡台差し止め」通告のため、大久保利通と共に長崎から東京に戻っていたリゼンドルは、1874(明治7)年7月12日付けの書簡に添付された7月8日付けの英文メモ・34号を大隈重信宛に送り、日本政府が政府新聞を発行すべく建策をした。少し長い引用になるが、メモの始めに 「政府の努力と要求が公式新聞紙上に明確に公表される事」で国家の信頼が高まると説き、続けていわく、
・・・いわば移行過程の国家である日本に於いては、諸外国からの信頼は特に大切で、不可欠でさえある。さて、日本政府がそんな信頼感の構築に向かいあらゆる事を行ってきたと断言するほど誰も軽率ではない。全く、現時点では世界の資本家がこの国に全幅の信頼を置いている事は明らかだが、若し政治問題が継続すれば、最大限の資源開発へ向けた日本への資金保証が出来なくなるだろう。
しかし世界の資本家の信頼にかかわらず、日本はまだ新しい国家だという事、一般に日本の状況を良く知らされている人でも現状を殆ど知らない事、多くの人々に日本は支那よりもっと閉鎖的であると思われている事などを忘れてはならない。そして日本は、こんな人々から資本を提供して貰わねばならないのだ。・・・現状では日本政府に対する万全の信頼があると言われているが、日本のように世界に対し本当に新しい国家は、その信頼に対し、破壊とまで言わずとも損害を与えるのに大したショックは要らないという事実を殆ど追加する必要もない。若しどの程度のショックが必要かと問われれば、横浜で発行される新聞類を塗りつぶせば良いだけである。知識もなしにただ待っている横浜の新聞発行人達は、あらゆる結果に全く無頓着である。そして、横浜の商人達は多くの理由から殆ど日本政府と国民に有害で、彼らは英・米両国の大衆に向かって日本は過剰に期待され、日本政府は弱体で、国の資源は少なく、新聞が書くように反乱と分裂の前夜である国に投資する如何なる資本も著しく危険だという意見を伝えようとする、そんな横浜商人達を喜ばす事だけを横浜の新聞発行人達は望んでいる。政府が投資を呼び込もうとする人達が、新聞で常に、国家は倒産に直面しその政府は虚構であるとする記事をまのあたりにしていれば、政府がいくら巧妙に施策を実行し国家の為に最善を尽くしていると考えても、意味の無い事である。そんな記事が如何に馬鹿げていても、日本を知り公正な意見を持つ人達はその馬鹿さ加減が分かろうが、依然として大衆はその記事を信じ、従って政府に害が及ぶのである。事実、これらの記事は決して反駁されないから、何処かおかしいとも思われないのだ。日本政府の支持を得ているという信用を持つ「ジャパン・メール」紙が、ある時は政府を支持していても、次いで歯をむけば、不快極まりなく全く身に覚えのない弊害になる。
こんな記事に対抗するには、日本政府が東京で自身の機関新聞を設立することである。自己利益の為に大衆の支持を仰ぐような経営をする横浜新聞では役に立たず、そんな新聞は後援者を確保する為に公的職務を思案せざるを得ず、従って政府に反対する事になるのだ。「ジャパン・メール」紙に要求される二万五千ドルもの巨額費用ではないもので、各省庁向けの全ての外国向け書式や書籍の印刷を賄えるだろう。これは月額八百ドル以下にはならないが、即ち、定期購読者などを合わせ、どんな損失も出さぬだけでなく、経験者に委ねて、利益を確保するようなものになろう。これを担保するため、この新聞の発行者として、横浜新聞に関わっただけの経験を有する素人の雇用では無意味である。この発行者はいわゆる経験者であらねばならず、プロ級にまで育てられ、英国や米国の第一級新聞で経験を積んだ人物でなければならない。・・・
そんな機関新聞が日本政府により所有され――政府の統制下で給与を得る編集者により発行される――べきである。我々は、横浜の諸新聞が如何に佐賀の乱や台湾出兵における日本政府の処置を誤解して来たかをみてきたが、今の段階では横浜新聞の記事があまり効果を発揮してはいないものの、しかし、チェックをしない限り、少しでも日本が遭遇する期待に反するものがあれば、理屈抜きに新聞により誇張され、日本と日本国民にとり最悪の有害事となろう。
1874年7月8日、東京にて。
この様に政府機関紙の重要性を綴っているが、この内容から、横浜の英字新聞の多くは日本政府を非難する論調の中にあっても、英国人のハウエル発行の 「ジャパン・メール」紙は日本政府に好意的で、政府も肩入れをしていたようだ。しかし、上述の如くリゼンドルは台湾出兵に深く関わり、自身では渡台出来なかったといえども、公式には蕃地事務局長官・大隈重信や事務都督・西郷従道の補佐であり、日本政府の台湾出兵にアドバイスを与える責任ある立場だった。従って台湾での日本軍による生蕃懲罰の結果や、清国はもとより、清国の陰にありそうなイギリスやアメリカなどの出方にも気を使い、日本国内では特に横浜の英字新聞の論調は大いに気になるものだったはずだ。
この一つ前のメモ・33号は同じ年の7月5日付けで、大隈重信に台湾出兵につき清国とどう交渉すべきかの意見を述べるものだから、その3日後に出したこのメモ・34号も全く台湾出兵に関連して書かれたと見てよい。「政府の支持を得ているジャパン・メール紙が、ある時は政府を支持していても、次いで歯をむけば、不快極まりなく全く身に覚えのない弊害になる」と非常な危機感を表明したのもこのためだったはずだ。だから、日本政府の外交政策の足を引っ張る可能性もある、治外法権に守られ一方的に日本政府を非難しがちな横浜の英字紙に対抗する、政府機関紙の発行を強く建策したのだろう。
(リゼンドルのメモ・34号:早稲田大学・古典籍総合データベース、大隈関係文書、Letters : to Okuma, S.、イ14 c0462。リゼンドルのメモ・33号:国立公文書館デジタルアーカイブ、[請求番号] 本館-2A-033-06・単00533100。)
♦ リゼンドル、ハウス、福地による政府機関紙発行の具体的提案
この頃の明治政府の財政は依然として農民からの税金に頼り、ちょうど1年前の1873(明治6)年7月28日に出された「太政官布告第272号による地租改正法令」で徴税制度としては出来上がったが、政府の財務内情は火の車だった。本サイトの「15、幻の改税条約」でも書いたように、9ヵ月後の4月25日、大蔵省租税頭・松方正義が大隈重信に宛て「輸出税則改定建議」を提出し、この省内の議論に基ずき、1875(明治8)年7月23日には大隈重信自身が外務卿・寺島宗則に宛て条約改正即ち海関税改正交渉の督促をするというほどに財政改善に向け議論が高まった時だ。そんな中での台湾出兵で臨時費用が重なり未だ結論も出ていない中で、蕃地事務局長官であり大蔵卿でもある大隈重信も、このリゼンドルからの政府新聞発行の建策を「尤もだ」とは思ったにしろ、自身で具体的な指示を出し行動に移す余裕も無かったであろう。従ってその実力を認めているリゼンドルに、その建策の具体化も任せていたように見える。
このメモ・34号の建策から9ヵ月後の、1875(明治8)年4月5日付けのリゼンドルから大隈重信宛の書簡には、具体的に採算を述べた収支見積もり実行案が提案されている。要約すると、いわく、
毎週新聞の発行についてハウス氏と福地氏と協議したが、その新聞は英語版で12面、日本語版で12面とし、重要記事は英語版と日本語版で相互に翻訳した同じ記事を載せ、英語版はハウスが、日本語版は福地が責任を持って編集し、これを日本政府の官吏が監督する。この新聞の費用見積もりは、英語版で1ヶ月当たり645ドル、日本語版で545ドル、合計1ヶ月当たり1,190ドルになる。年間購読料は英語版で1部20ドルとし、年間最低1万2,200ドルの売り上げを期する。日本語版の年間売り上げは英語版より少ないだろうが、かなり期待できるだろう。福地によれば日本語版は、場合によって1ヶ月6回の「一、六日」を発行日とし、紙面縮小版で費用を同額に維持する案もある。
この様に大隈重信は当時、エドワード・ハウスや福地源一郎とチームを組んだリゼンドルの具体的な提案を受けたが、政府機関新聞発行はなかなか結論に至っていない。
この時どんな経緯でリゼンドルのチームに福地源一郎が加わったのか筆者には定かでないが、当時このリゼンドルの書簡が書かれた明治8年4月頃、福地は大蔵省を辞任後の明治7年12月から加わった東京日々新聞の主筆・社長であったはずだ。福地源一郎著の『懐往事談』(東京:民友社,1897年)の後半に附された「新聞紙実歴」の部分に、「常に伊藤伯など在朝の諸公を訪問し・・・当時政府に官報がなかったので政府に乞い、東京日々新聞に太政官記事御用の称えを得て、官報の用に充てようと試みた」と書いている頃のことだ。従ってリゼンドルやハウスと収支見積もりを協議したのは、福地が大蔵省を辞任したあと東京日々新聞に参加するまでの頃の事だった様に思われる。
♦ エドワード・ハウスの独自調査と国内新聞取り締まり条例
また2ヶ月ほど経った同年6月20付けでリゼンドルは大隈に宛て、当時ハウスが独自にコンスタンチノープル駐在アメリカ公使の協力で調査した、トルコ政府が採用した外国新聞取締りに関する「新聞発行の全面停止」処置をも含む出版条例の内容を参考として送ってもいる。トルコでは、政府の意に適わない外国新聞は出版禁止に出来るという情報だ。
この頃またエドワード・ハウスは、この治外法権を最初に日米修好通商条約に盛り込んだ張本人である、当時の日本駐在アメリカ総領事でニューヨーク在住のタウンゼント・ハリスに直接書簡を送り、「貴下はこの恥ずべき治外法権導入は永久処置ではないと思っていたはずだが、貴下の心情をお聞かせ願いたい」と書き送った。ハリスは返書で、「そもそも自分が日本に派遣される前に当時のマーシー国務長官と会談したが、治外法権なしに東洋諸国との条約締結は出来ないと言われた」と述懐し、過去のトルコやペルシャ、アフリカのバルバリイ等との条約が先例となりこの治外法権項目の挿入が不可欠だったのだろうと思うが、偏にこれが除去されることを願うと述べている。この往復書簡の写しもトルコ出版条例と共に同封され大隈に届けられている。従ってハウス自身もまた、日本が強いられている治外法権と制御できない横浜の英語新聞の問題に強い問題意識を持って独自調査をし、既に引退してニューヨークに住む元アメリカ公使のタウンゼント・ハリスにまで手紙を出したのだろう。後に触れるが、ハウスはこのハリスとの情報交換書簡を、その後繰り返しその論文に登場させている。
この間に日本国内では、国内発行の新聞を取り締まる目的で明治6(1873)年10月19日に布告されていた「新聞紙発行条目」が改正され、明治8(1875)年6月28日に「新聞紙条例」が布告されより厳しい制限が付くようになった。しかし横浜で外国人の発行する新聞は依然として治外法権で守られ、日本国内向けの「新聞紙条例」が適応できなかったから、未だリゼンドルが指摘した日本政府を俎上にあげる横浜の外国語新聞の問題点は未解決だった。
(新聞採算見積もり書簡:早稲田大学・古典籍総合データベース、大隈関係文書、新聞発行収支見積書、請求記号:イ14 a4441。トルコ政府の出版条例:同上データベース、大隈関係文書、土耳古帝国新聞紙取締法ヲ上ル書、請求記号:イ14 a4443。)
♦ 再度の提案と推薦されたエドワード・ハウス
政府新聞を何とか実現する必要があると固く信ずるリゼンドルは、具体的な計画を提出しても明確な結論が出ない日本政府の動きにも、この推奨計画を諦めてはいなかったようだ。ほぼ1年も経つ頃、ここで再度またリゼンドルから大隈宛に出された、1876(明治9)年3月5日付けの覚書第52号の概略内容は次のようなものだ。いわく、
ジャパン・メイル新聞所有者の代理人であるジョン・ピットマン氏は、W・G・ハウエル氏が所有する新聞の社業を1万5千ドルで早急に譲りたいので、(ハウエル氏から)自分(リゼンドル自身)と交渉するよう依頼された、と告げてきた。今迄にも日本政府のため機関新聞が必要な事は説明してあるが、あるいは閣下の意に沿うのではないかと考えこの返事を保留してある。ハウエル氏が新聞を手放すことは間違いなく、従って売値の1万5千ドルは交渉の余地があると思う。この新聞社の財務内容詳細を調べたい。
新聞記者の経験や文章の才能において、また日本の主張やその進歩発展を願う気持ちにおいても、(政府がこの新聞を買収した後)自分の知る限りこの編集事務を託せる唯一の人物は、E・H・ハウス氏以外にない。閣下が了承できれば、ハウス氏と話をしてみたい。
若し日本政府が直接関与する事が問題なら、民間で華族などの出資を得て、会社組織で運営するという可能性もある。
ハウエル氏は帰国を急いでいる様子で、自分(リゼンドル)個人が買収すると思って特別に依頼してきたので、至急否やの回答をお願い致したい。
この様に、既存の新聞社買収と言う更なる具体的な提案が出されたのだ。これに対し大隈は、リゼンドルに3月9日付けで直ちに返書を送り、
貴下52号の覚書、新聞譲受一件申立ての趣、詳悉せり。予に於いても久しくその必要なるを知るを以て、政府の利益を謀る広告具 (筆者注:新聞等の広報手段) を設立するの企て無きに非ず。・・・貴下速やかに着手して極低の價値と真実の計算とを精査して報告せらるべし。彼の編集者人選の(一件に付き?=判読不可)、予に於いても全く異存なし。
と、その調査・交渉の具体化を了承し、編集をハウスに任せることに依存はないと告げている。
筆者には、このリゼンドルの覚書に出てくる「ジャパン・メイル新聞所有者の代理人ジョン・ピットマン」と新聞所有者のW・G・ハウエルや、この2人とリゼンドルとの関係が良く分からない。しかし、台湾出兵の決着を付けるため大久保利通自身が清国と交渉する時期、即ち明治7(1874)年10月11日から14日の大久保利通の日記に、ピットマンが大久保の意を受けて、大久保と清国駐在イギリス公使・ウェードとの間を往復する記述があるから、ピットマンは大久保の信頼を受け陰で手助けしていた人物だ。また明治9年3月12日付けで大史・土方久元(内務省)から右大臣・岩倉や参議・大久保、大隈、伊藤に宛てた「清国事情報知の為、英人ピットマンに手当金1ヶ月250円を出す」という許可願いが出されていることなどから、当時ピットマンは上海在住の英国商人として、大久保利通、大隈重信、伊藤博文などと強い繋がりのあった人物のようだ。またしばらくしてジョン・ピットマンは、内務・大蔵両省のお雇いにもなった人物だが、このように大隈も良く知っているピットマンの仲介だから、直ちに了承したのだろう。
(リゼンドルの覚書第52号と大隈の返書:早稲田大学・古典籍総合データベース、大隈関係文書、ジャパン・メール新聞譲渡ニ関スル往復書翰、請求記号:イ14 a4455。大久保利通の日記:「大久保利通日記、下巻」、日本史籍協会、昭和2年4月25日発行。英人ピットマンへの手当金:国立公文書館、ディジタルアーカイブ、畢徳曼来翰、[請求番号]本館-2A-034-01・単01378100。ジョン・ピットマンお雇い:「資料御雇外国人」、小学館、昭和50年。)
♦ エドワード・ハウスとの「東京タイムス」紙発行の助成契約
この大隈重信の返書を手にしたリゼンドルは、早速エドワード・ハウスと横浜に行き、ジャパン・メイル社の財務内容の調査を始めた。しかし内情を調べた2人は、がっかりする事になる。
それは半年ほど経った1876(明治9)年9月、リゼンドルから、大隈重信と近い関係にあったと思われる当時の内務少史・平井希昌(ゆきまさ)宛ての書簡で、「横浜で(ジャパン・メイル紙の)実地検査をしたところ、その不利益なる事が分かり、ハウス氏は既に買収の件を断念した。・・・しかし若し日本政府がこの新聞を買い取る決定をすれば、ハウス氏が記者を務める可能性は今後の話し合いで可能であろう。ハウス氏と自分の意見では、別に新たな新聞を立ち上げた方が得策と思う。若し日本政府が1年に6,500ドルの補助金を給與するなら、ハウス氏は新聞の営業を始め、ハウエル氏と同様、新聞500部を献上する。本件を大隈閣下へお伝え願いたい。」と云うものだ。
この時は既に、リゼンドルとハウスに任せようと大隈重信の腹は決まっていたように見える。早速その内意を受けたであろう平井希昌から明治9(1876)年10月11日付けの内密議案 「米人ハウス刊行の毎週新聞へ助成金資給の儀に付き命令書案」が大臣と参議宛てに出され、岩倉具視、大久保利通、大隈重信の許可を受けた。これに基づき早速10月15日にエドワード・ハウスと交わされた、新聞発行と政府助成金支給に関する契約書は次のようなものだ。いわく、
日本政府の代表者たる参議兼内務卿大久保利通閣下、参議兼大蔵卿大隈重信閣下の命に因り、少史平井希昌、貴下、この命令書を履行せり。日本通用銀貨壱萬五千円額をイ エッチ ハウス氏の東京に於いて編緝刊行する毎週新聞の助成として、これを二十八期に割賦し、その第一期壱千五百円額はこの書調印の第二日に資給し、その第二期以降は調印の時より三個月の後に始まり、五百円額を月月資給せらるべし。因てその為め契約せらるる條款を開載する事下文の如し。
と記述され、新聞の発刊は契約日から45日以内に行う事、毎号500部は無償で政府指名の受取人へ届け、海外諸国への送料は毎年銀貨500円の郵便料金を別途受け取る事、大久保、大隈、鮫島閣下の特別に公布したい記述や口演内容は直ちに掲載する事、日本関係の諸説諸意見はハウスの見識の及ぶ限り常に政府の裨益(ひえき、=役立つこと)を考え真実公正で偏頗(へんぱ=偏り不公平なさま)なき事など、第1条から第9条まで載っている。
従って契約期間は、この1万五千円の助成金を30ヶ月、即ち2年6ヶ月の間支給するという、明治12年3月までの契約である。これはその後1年半ほど経った明治11年4月26日、平井希昌から内務卿・大久保利通と大蔵卿・大隈重信宛てに、年間1千円を増額し明治13(1880)年3月まで更に1年間契約を延長すべく申請が出され、許可されている。しかしこの延長契約書に政府高官の名前はなく、三井銀行取締役・三野村利助とハウスとの契約調印になっている。これは何らかの理由により、日本政府の助成を表面に出したくない事情が出来たのだろう。あるいは、当時の外交関係で完全自由貿易を言い募るイギリスへのエドワード・ハウスの攻撃記事の掲載で、「日本政府が陰で糸を引く新聞」だなどと噂が出たのかも知れないが、筆者はその詳細を知らない。
ところで、買収案が出てこのハウスに嫌われた「ジャパン・メイル」紙は翌年の1877(明治10)年1月までW・G・ハウエルにより続けられ、その後数回所有者が代わり、1881(明治14)年にイギリス人のフランシス・ブリンクリーに買われた。そして横浜の3大英字紙の一つとして、また親日的な論調でその名前が知られるようになったという。
(リゼンドルから平井希昌宛て書簡:早稲田大学・古典籍総合データベース、大隈関係文書、新聞発行ニ関スル書翰−平井外務大丞宛、請求記号:イ14 a4456。ハウスとの契約書案:同上データベース、大隈関係文書、米人ハウス発行ノ新聞ヘ助成金下附ニ関スル命令書案、請求記号:イ14 a1115。1年延長契約:同上データベース、大隈関係文書、東京タイムス助成金増額契約ニ関スル伺書、請求記号:イ14 a1116。)
♦ エドワード・ハウスの「東京タイムス」紙の創刊
さてここでは本来、リゼンドルの政府新聞発行の建策が出されてから2年6ヵ月後に実現したこの「東京タイムス紙」の内容や、ハウスの主張とその時代背景を書くべきだが、現在の筆者にはこの新聞を目にし読む事が驚くほどの難題で、例えば飛行機に乗って行くほど遠方の図書館に保存されていたりして、なかなか手が届かない事が分かった。上述の如く毎号500部も明治政府が買い上げ、年間500円もの大金を掛けて海外にも郵送したものだが、残念ながら何処でもあまり保存されなかったのだろう。筆者に大きな課題が残ったことになり、これを将来に残しておく。
さて、上述の如くエドワード・ハウスが買収を嫌ったジャパン・メイル社が、明治10(1877)年1月6日から発行が始まったハウスの「東京タイムス」創刊第1号についてコメントを掲載している。同じ日付けの「ジャパン・ウィークリー・メイル」紙中の第2面、右欄下方の「週間記録」中の記述だが、いわく、
今日の午後東京タイムス紙の第一号が姿を現したが、我々は最近ここでは既に余りにも多くの新聞があり過ぎると云う意見を述べていたからといって、心からの歓迎を拒むべきではなかろう。その記述が滑らかかつ簡明で、しかも素晴らしい感触である事から、その紙面が編集者の能力を十分に証明している。既にキーノートが示すように、恐らくこの新聞で力説される見解は、条約中の治外法権に関する条項の削除と、この国の貿易は純粋な保護貿易関税に基づく必要性についてであろう。第一点に関して我々は、この願わしい状況が達成されるか、或はまた、我々と日本人との訴訟問題が信頼の上に立って処理される、外国人に対する充分な保障が出来る混成裁判官制の確立といった、更に現実的な形で処理できる時期に至っていることを心底願うものである。(外国人同士の訴訟において、一部でさえ日本人裁判官が関係する裁判に充分委託できるとは、まず考えられない)。しかし、現今ではこんな混成裁判官制は全く機能しないことは経験上明らかで、暫くの間今の世代がいる間は、まして純粋な日本人裁判官だけの法廷などは考えられない。第二の問題に関しては、最近の英国でアメリカで適応された保護関税方式の結果につきさんざん議論された問題で、その制度の支持者により議論が打ち切られ過去のものになったものだが、アメリカではそのやり方で疑いもなく自国市場を制したとは言え、世界の別地域でアメリカがイギリスの競争に打ち勝ち得るという気配さえなく、今の所、勿論アメリカがずっと安く買えた全製品に途方もない高値を払っていると、その何時もの手法で経済学者が最近分析済みである。合衆国では自由貿易推進組が急速に拡大している事は確実で、ある種の最も雄弁で強力な誤信への反証が保護貿易主義全体に内在している事もまた確実だとアメリカ人は言っている。我々は、この様な事実がこの問題を決定づけると言い張るべきではない。しかし我々はこんな事実が、如何なる思慮深い人をも、全世界の高名な経済学者がかって魅惑的で破滅的な誤信により苦しめられたのだと考える方向に向かうと断言はできる。
この様に、新しい新聞の出現に歓迎の意を表明し編集者は優秀だと称えこそしたが、治外法権条項の削除と貿易保護関税の導入という 「主張の意図は分かっているぞ」、「主張はそう簡単には行くまい」と手厳しく言及した。
本サイトの「15、幻の改税条約」でも記述済みだが、当時ハウスの発行した1月27日付けのこの東京タイムス紙第3号に載った明治政府の税収入について、アメリカ公使・ビンガムでさえ本国の国務長官宛てに、「(日本政府の)今会計年度予想歳入表に依れば、輸出入税の予想歳入はただの$1,762,554で、同年度の予想租税歳入は約$61,000,000ですが、その中、$46,556,743が国民に課せられた地租です。私がこのように言うのは適切だと思いますが、日本で種々の貿易にかかわる外国人は、彼らが言う所の1866年の貿易約書を根拠に、その巨大な利益や収入に対する税金は何も支払っていません」と報告するくらい、税率の低さは注目を集めた問題だった。貿易関税が安すぎて、国家租税歳入の3%にも満たない低額で、ビンガム公使もびっくりして報告したものだ。
またその中で同様に記述済みだが、明治11(1878)年11月7日付けの駐英公使・上野景範から外務卿・寺島宗則宛の報告書翰に、「当国の外務卿輔に於いてはあくまでも自由貿易の主義に固着し・・・喋々(ちょうちょう、=口数の多い事)保護税法の非なるを弁論相成り、・・・保護税法に類するの件は一切承諾いたし難しとの事にこれあり・・・」と報告された様に、イギリスは完全自由貿易論を譲らず、日本の導入しようとする貿易保護関税を含む条約改定を頑なに阻止し、結果として、当時の条約改定交渉責任者の外務卿・寺島宗則を辞任にまで追い込んでいたものだ。
このハウス発行の「東京タイムス」紙は、上述の如く、明治13(1880)年3月までという明治政府との助成金支払い契約期間が終了し、明治13年6月をもって廃刊になった。それ以降の助成金再交付や延長は無かったわけだ。この後、程無くハウスはヨーロッパとアメリカに渡航し、日本の為に情報収集と宣伝活動をするが、それは下記に触れる。
エドワード・ハウスの日本外交関係の著述と論文
♦ エドワード・ハウスへの年金支給
少し唐突で先走る記述になるが、エドワード・ハウスは持病として痛風を持っていたようだ。時に発作を起こすと痛くて歩行困難をきたす痛風がハウスを苦しめ、晩年には歩けなくなったと聞く。本サイトの「17、特派員、エドワード・H・ハウス (その1)」でも書いたように、明治6(1873)年1月28日付けで大学南校教授を辞めアメリカに帰国した時も、「病気の故を以て継続無しの満期解雇」になっているから、単なる辞職の理由付けに使っただけでもなさそうだ。当時のデロング公使がハウスの解雇を日本政府に迫ったという理由だけでなく、理由の半分は既にこの通風も出ていたように思われる。
とに角また、この通風が再発した。明治16(1883)年11月29日、外務卿・井上馨から 「米国人ハウス氏、年金給與の儀に付草す」と題するハウスの功労に報いる年金支給の建議が出され、許可されている。いわく、
米国人イ・エッチ・ハウス儀は、明治四年我大学南校の教師と為り、勉励事に従い、又平素我国益を計考し、外国の関係に意を注ぎ、其身従来米国一二大新聞の通信員たりしを以て、其慣手の筆鋒を揮い、常に反対論者を攻撃し、務めて我国権を拡張するの真意を表せり。明治十一年中、特に政府の内命を承け、毎週新聞(東京タイムス)を発刊し、苟(いやしく)も我邦の利害相閉さんに逢えば、直言痛論豪も忌憚せざる所なり。為に一二駐剳(ちゅうとう)の外国使節の嫌悪する所となるも、私を以て公に屈せず。其行為或は他人の謗識(ぼうしき、=非難)を来たしたる事有之と雖ども、其哀情に至つては嘉称(かしょう、=ほめたたえる)すべきものに有之。且又先年、米国大統領グラント氏、香港知事ヘネシー氏渡来するに、方々此両氏等と親昵(しんじつ、=昵懇)の交誼あるを以て、其誘導に因り、政府の内意に依り、自費を以て各国を巡遊し所在の政権家若しくは有力の新聞記者等に相交り、我国の為めに各国の輿論を傾向せしめん事を勉めり。又曽て馬関事情と題せる小冊を編述し、之を世に公にし、世人の尚来る此議に注意せざるに先ち、大に米国の輿論を聳動(しょうどう、=驚かし動揺させる)せしめたりき。米政府の昨年償金を返還するに決定せしも、我外交の効験と米政府の公平なる果断とに依ると雖も、亦ハウス氏賛助の効、決して他の賛助者に譲らざるべしと存候。十五年秋再び文部省の嘱託を受け、大学文学部の教師たりしに、病の為めに之を辞し尚病床に在り。近日養痾(ようあ、=病気の療養)の為め欧州に赴かんとするも、其資料(=もとで)充分ならざるが為めに未だ其意を果たさず。目六(=経済事情)困難の事情相聞候。然るに従来同人の履歴を観察するに、先年我政府の内命を承り、当時廟議の機密をも幾分預漏聞致居り候者とて、萬一右等困難の事情より、其志操を他に転じ候様の事至し候ては却て我邦の有害と相来し候間、一は以て前記我政府の内命(大久保、大隈両参議当時之を伝ふ)ありし新聞の刊行、馬関償金の件に関する編述及び欧米巡回の件其他多少尽力の効労に酬い、一は以て後来我邦に遣害せざらしめん為に、馬関償金の内ら以て一ヶ年金貮千五百円宛、明治十七年より向う七ヶ年間特別を以て御給與出来度。氏儀御裁可の上は、別紙甲号案之通り内翰を添え、乙号之通り年金給與證書を御付與出来度。同人欧州出立之期も可成り相急ぎ居候間、前述之情状御諒察の上、至急に御裁決出来度、此案草し候也。
明治十六年十一月廿九日
外務卿井上馨
太政大臣三條實美殿
上申之趣聞届、金額支出方の儀は別紙の通り大蔵省へ相達候事。
明治十六年十二月廿一日
この様に当時の外務卿・井上馨は多くのハウスの功績を列挙し、明治政府は、病のため経済的に困窮するというハウスに年間2,500円という年金を7年間も給与すると決定したのだ。「困窮のあまりハウスが過去の機密事項を漏らさないように」という理由付けには首を傾げたくもなるが、こう表現するほど当時のハウスは明治政府の外交の中枢に関与し、井上馨や大隈重信等と云う、当時の明治政府の中枢が如何にハウスの陰ながらの働きに感謝し、その功績を高く評価していたか良く分かる行為である。また井上外務卿が、「馬関償金の内ら以て一ヶ年金貮千五百円宛」を給与したいと提案したこのアメリカ議会と政府が日本への返還を決めたた 下関賠償金(筆者注:ここに戻るには、ブラウザーの戻りボタン使用) は、1883(明治16)年4月22日付けの井上外務卿のアメリカ公使宛の書簡で受け取り了承をしていたから、この時はすでに78万5千ドルの小切手が日本政府の手に渡っていたわけだ。また直ぐ下に書く通り、何とか排除したいと思っていたイギリスのパークス公使も清国に転出した直ぐ後だったから、ハウスを顕彰する絶好のタイミングだった。大学南校あるいは東大で月額250円(又はドル)ほどの給与を受けていたから、その80%にも当たる高額年金額だったわけだ。ハウスはこの頃再度10年ほど故郷のボストンに帰っているが、おそらくこの年金を原資に病気療養をかねながらであろうが、多くの文筆活動を行っている。
(外務卿・井上馨の年金給与建議:国立公文書館、ディジタルアーカイブ、米国人ハウスノ功労ニ報酬シ年金給与ノ件、[請求番号] 本館-2A-001-00・別00012100。)
♦ エドワード・ハウスの欧米向けキャンペーン
ここでは、当時の外務卿・井上馨がハウスに年金まで用意したその功績の一部を探って見たい。
上述した東京タイムスの明治政府との助成金支払い契約期間が終了しての廃刊後、ヨーロッパとアメリカに渡ったハウスは、イギリスが強硬に自由貿易主義を堅持するため日本は条約改定が出来ず、即ち関税の改定が出来ず、また治外法権も回復できず、行き詰まった日本外交を背面から援護すべく情報収集と宣伝活動をしたのだ。このためハウスが書いた論文のいくつかは下に記述するが、それがどれほど有効だったかはともかくも、ハウスが再び欧米から日本に帰って来た翌年の明治16(1883)年7月、あるいは、このハウスへの年金支給に関する井上馨の建議書が出される4ヶ月ほど前、その昔の慶応1(1865)年閏5月の赴任以来18年間にも渡り、あれほど長く日本外交を苦しめて来たイギリス公使・パークスがついに日本公使から清国公使に転出したのだ。
この転出とその背景に関してはしかし、当時熱心に条約改正交渉に取り組み、従ってパークス公使に甚く苦しめられて来た井上が書いたハウスへの年金支給建議書の文中には、当然ながら具体的に一言も出て来ない。しかし筆者は、ハウス論文とそのキャンペーンがパークス公使の日本政府への態度を大幅に改善させ、その後の転出に大きな影響を与えたという事情も、ハウスへの年金支給を後押しする主要理由の一つだったのではと考える。その証拠として、井上が英国駐在の森公使に送った明治15(1882)年3月31日付けで条約改正の2大方針を通知する書簡の最後に、
パークス公使も近来大いに面目を改め、協和を主とするように相見え、万事協議も致し易く、好都合にこれ在り候。
と書いた通り、本国から帰った後のパークスの態度が大きく変わっていたからである。この理由は、下のハウス論文 「帝国の苦難」の最後に書く通り、このハウス論文の為にイギリスでパークスを巻き込んだ一大論争が起き、パークスはその態度を改めざるを得なかったのだ。そしてついには、日本公使から清国公使に転出したのだ。
この井上馨の建議書に書かれた様に、困難に遭遇する日本外交を背面から援護する情報収集と宣伝活動の一環として、ハウスはいくつもの論文を書き発表している。勿論こんな政治的なもの以外にも、知人の日本の医者や政治家、日本の芝居や文化・紀行など文学的な著述もあるが、以下に、この章の主要題目である政治・外交に絡んだ論文に付き触れて見たい。
(井上が英国駐在の森公使に送った明治15(1882)年3月31日付けの書簡:外務省、日本外交文書デジタルアーカイブ、第15巻(明治15年/1882年)。)
♦ 『日本の現状と将来、(The Present and Future of Japan)』 − 明治維新とハウスの日本への期待 (1873年5月)
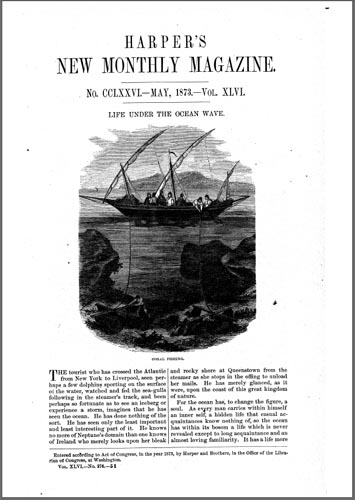 Harper's New Monthly Magazine
Harper's New Monthly Magazine
Vol. 46, Issue 276 (May, 1873)
Image credit: Courtesy of
Cornell University Library
明治維新の信じ難いほどの激変と、ハウスが懸念する 「少しその速度を緩める必要性」を記述したこの「日本の現状と将来」と題する論文は、アメリカの「ハーパーズ・ニュー・マンスリイ・マガジン」誌の1873(明治6)年5月号に掲載された。1850年創刊のこの雑誌は、ずっとアメリカ東部の裕福で教養豊かな知識人を読者にした、専門家や知識人による読者啓蒙の雑誌である。こんなメディアに掲載されたエドワード・ハウスの論文は、多かれ少なかれアメリカのオピニオン・リーダー的性格があり、当然その影響力もあったと思われるものだ。
ハウスいわく、それまで2世紀半にも渡って保持されてきた体制が、過去6年間ほどの間に大変革をきたした。これは他国では何年も何世代もかけ多くの犠牲者を出したほどの改革が、日本では1日で、しかも国内の平和を乱すことなく行われた。日本のこんな国家体制の大転換は、近代社会の不思議とも呼べようと記述している。それまで飾り物にすぎなかった天皇が自ら国政を取り、身分差別を撤廃し、下層階級が侍と同様に大道りを馬に乗り上等な着物を着ていたり、一方の侍は廃刀までしたのだ。身分差別撤廃は、皮革業に従事し歴史的に虐げられ差別されてきた穢多にまでも及び、この差別を一日で無くしてしまった。国内の騒擾が全て無くなった訳ではないが、日ごとに収まっている。未だに統制色の濃い規則は、旧大名の首都在住を求めるものだ。この様に大改革が進められ今日に至ったが、現在の議論は、如何にして直ちに全国に外国流の法律を適用し、外国人に開放し、自由な商いに委ねるかである。日本政府の財政は困窮しているが、日本はこれまであらゆる方面で外国勢に裏切られ、貿易に障壁があっても外国公使たちは容認している。条約に記載された日本にとっての重要事項ですら、言外に信頼を寄せる各国政府から説明もなく無視されているから、日本は全て外国頼みに出来ない事は良く知っている。ハウスはこの様に記述した後、全世界で最先端を行く各国の後を追い、対等の位置に着く前に、日本は大改革で緩んだ足元を固める自覚が必要だと説く。日本の現状について語るならば、その行く先を注意深く思いやりのある態度で見守るべきだ。どんな国の如何なる将来も断定できないが、日本は色々な困難を乗り越え、世界の先進国中でも立派な、卓越した地位にまで到達するだろうと結んでいる。
この論文が発表された1873年5月という時期は、本サイトの「17、特派員、エドワード・H・ハウス (その1)」に書いたように、ハウスがジャーナリストとして、マリア・ルス号事件でアメリカのデロング公使が取った態度を痛烈に批判し、デロングが日本政府にハウスの大学南校からの追放を迫り、病気を理由に教師を辞任したハウスがアメリカに帰国していた時期である。
(「The Present and Future of Japan」: Harper's New Monthly Magazine、 Volume 0046、 Issue 276 (May, 1873)、 [pp. 858-864]、Author: House, E. H.)
♦ 『下関戦争、(Simonoseki Affair)』 − 下関戦争と賠償金の正当性の検証 (原稿:1874年11月、英語版発行:1875年4月)
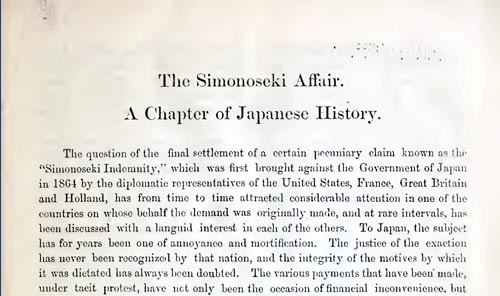 The Shimonoseki Affair
Image credit: Courtesy of The Internet Archive
The Shimonoseki Affair
Image credit: Courtesy of The Internet Archive
下関戦争の背景やアメリカ政府によるその賠償金返還については、本サイトの「6、薩英戦争と下関戦争」及び「14、下関賠償金の返還」に既に書いた。この賠償金の支払いは、旧幕府が半分だけ支払ったが、残り半分の支払い責務が明治新政府に持ち越されていたのだ。この残金について明治5(1872)年4月2日、当時の副島外務卿からアメリカ、イギリス、フランス、オランダ4カ国公使宛に、当時外遊中の岩倉大使と各国政府が話をする予定なのでそれまで待って欲しいと書簡を送り、夫々から自国政府に連絡する旨の回答があった。岩倉のイギリスでの交渉で外国人の内地旅行制限の撤廃などの条件が出されたが、直ぐには出来ない条約改定が絡み、また双方の誤解などから、明治政府はイギリス、フランス、オランダ3カ国へ残金全額の支払いを決断した。これを知ったアメリカからも、明治7(1874)年6月10日付けのビンガム米国公使より寺島外務卿宛の書簡で、「米国政府の訓令に基ずき、下関事件償金残額は他の諸国と同様に受け取りたい」との申し出があり、明治政府はアメリカへも7月末をもって支払いを完了した。
しかし一方、アメリカ国内では「下関賠償金の返還」で書いたように、これ以前から、即ちアメリカ議会の下院で1870(明治3)年2月7日、日本が支払った賠償金をそのまま国庫に入れる議案が提出され、反対八十四、賛成八十一、棄権五十二でからくも否決されていた。そしてそれ以降の議会では、この償金の日本への返還方法が議論の中心になっていたのだ。
そんな中でアメリカ公使から賠償金残額の支払い完納要求が出され、日本政府はその支払いを終えたわけだ。外交の論理を別にすれば、一見してこれはアメリカの大きな矛盾だと映るが、ハウスのこの「下関戦争」の日本語の原稿に 「千八百七十四年十一月東京に於いて」 と日付を入れてあるから、日本政府がアメリカ向けの賠償金残額を7月31日に横浜・オリエンタルバンクに振り込んだ時から約4カ月後の日付けである。明らかに、ハウスがこの論文・「下関戦争」の原稿を書いたのは、賠償金残額のアメリカへの支払いに触発された事は疑いないが、ハウスがこの賠償金に関する調査を始めて原稿を完成するまでに、この4カ月弱が充分な期間であったのか筆者には分からない。しかし引用されている内容などから見ると、もっと早くから、即ち上述の如く、明治5(1872)年4月2日付けで副島外務卿がアメリカ、イギリス、フランス、オランダ4カ国公使宛に書簡を送った頃から構想があったようにも見える。
ところでハウスのこの「下関戦争」の原稿は、リゼンドルから大隈重信宛の1874年11月28日付け書簡に添付され、大隈にも届けられた。恐らくその原稿がまず日本語に訳され、関係者に回覧された様だ。アメリカやヨーロッパ向けに配布したいハウスは、まず日本で内容の確認を取ったようにも見える。外国向けに日本で印刷された英語版には、「1875年4月、東京にて」と日付が付けられている。
さてハウスは、次のように論じた。アメリカの議会や公共出版物などで繰り返えされる、下関賠償金の残額を免除し更に支払い分さえ返還しようという議論の最中に、アメリカの公使が他国と同様に全額の支払いを求めるに及んで、支援し鼓舞してくれるアメリカは特別だと思っていた日本は、幻想を抱いていたのかとショックの只中にある。しかし今や償金の全額が支払われ、事件の幕が引かれようとしている。このままでは、漠然と落ち度は日本にあったという事になり、日本に駐在した各国外務省の代表者たちの不法さは吟味されずに終わってしまう。こう書き出して戦争の経緯と賠償金支払いの要点を箇条書きにまとめた。そして、長州から最初の砲撃を受けなかったイギリス公使の主導で軍艦を下関に送り、戦端を開いたが、そもそも関門海峡や豊後水道、また鳴門海峡や明石海峡を通り瀬戸内海に出入りする地政学的状況は、丁度トルコのマルマラ海に出入りするダーダネルス海峡とボスボラス海峡の状況と非常に似ていると指摘した。国際法の原則は陸地から海上へ1リーグ(=約5.6km)以内はその国の領海だから、トルコとヨーロッパ諸国との条約を当てはめても、米、仏、蘭の船が長州に砲撃された下関の海上は純粋に日本領土内で、外国船が条約の取り決めも無くそこに侵入し砲撃されても、その全てが日本の落ち度だとは言えない。こうトルコのマルマラ海の例を引き合いに出した原則論を述べた。そして償金支払いまでの歴史的経緯も述べた。
そして最後をこう結んでいる。いわく、「前述したように、4カ国のどこかの国が自発的に新しい活力を注入しない限り、これで下関戦争の歴史的記述は終わる。それ(4カ国のどこかの国が自発的に新しい活力を注入)はまず有り得ないし、若し有ったとしても、賠償金を取った後に最高に満足出来る結果が来る事などは決してない。肉体が切り刻まれ多くの血が流されたのだ。誰がその傷を上手にそっと癒し得ると言うのか。長い年月に渡る屈辱と虐待で残された消すに消されぬ傷口を、どんな技で隠せると言うのか。・・・(この記述には限られた資料しかなかったが)何世紀にも渡る闇夜から抜け出そうと奮闘し、文明国の中でも尊敬されるべき地位に身を置こうと奮闘する日本が、世界の先進国からどう励まされ激励されてきたか、公正な読者の判断に委ねるには充分であろう。この下関の記録は、” 強国と云う堅固な基礎に立脚した外交 ” によって友好関係と互恵を推進するという、ほぼ20年に渡って使われて来た一方式である」。
筆者はこのエドワード・ハウスの結びの記述に大いに心を動かされるが、単に日本を擁護するだけの記述に止まらず、ハウスの因って立つ正義感や心情を垣間見る思いである。このハウス論文がアメリカ国内向けにどれほど影響力が有ったのか筆者には良く分からないが、とに角この論文以前から、14、5年にも及ぶ長い議会議論の末にアメリカ議会と政府は日本へ賠償金額の全額返還を決定し、議会で1883(明治16)年2月22日に返還法案を制定し、2月23日アーサー大統領が署名し、78万5千ドルが日本に返還されたのだ。上述の 「エドワード・ハウスへの年金支給」 に述べた如く、外務卿・井上馨はこのハウス論文が下関戦争賠償金の全額返還に貢献したとして、「我外交の効験と米政府の公平なる果断とに依ると雖も、亦ハウス氏賛助の効、決して他の賛助者に譲らざるべしと存候」と書いて高く評価し、この 「馬関償金の内ら」 年金を支払いたいとまで提案したのだ。
(「下関戦争」の日本語翻訳版:早稲田大学・古典籍総合データベース、大隈関係文書、下関償金一件 、請求記号:イ14 a4411。
「下関戦争」の英語版:「The Shimonoseki Affair. A Chapter of Japanese History.」、E. H. House、Tokio, April, 1875。)
♦ 『帝国の苦難、(The Martyrdom of an Empire)』 − 保護関税と治外法権 (1881年5月)
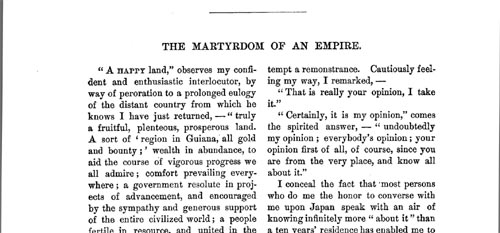 The Atlantic Monthly, Volume 47, Issue 283 (May 1881)
Image credit: Courtesy of Cornell University Library
The Atlantic Monthly, Volume 47, Issue 283 (May 1881)
Image credit: Courtesy of Cornell University Library
アメリカ東部のボストンで1857年に創刊された月刊誌「アトランティック・マンスリー」は、文芸評論誌として評判が高かったが、その後雑誌の性格も少しづつ変化し、一般評論誌として外交、政治、経済、文化等を扱ったという。読者層はやはり東部の、教養豊かな知識人であった。日本の財政難や治外法権に苦しむ現状を伝える、このハウスの「帝国の苦難」が載った1881年5月号にも、「文芸、科学、芸術、政治の雑誌」と銘打ってあるから、ハウスの日本関連の論文も編集者に歓迎されたのだろう。
東京タイムス廃刊後、ハウスが久しぶりにアメリカに帰って来て邂逅した昔からの知人で、気持ちよくその採用を決めてくれたアメリカ東部の玄人から、この人物は月刊誌「アトランティック・マンスリー」の編集者と思われる人物だが、現状の日本がどんな逆境にあり、不当な苦痛と屈辱からどう抜け出られるのか簡便に書いて見てくれと言われた、との書き出しでこの記述が始まる。
ハウスいわく、簡単に言えば、明治維新この方日本は極貧でお金は一銭もなく、かろうじて国家の体面を保っている状況だ。ペリー提督の遠征で日本が開国した後、タウンゼント・ハリスの並々ならぬ努力で通商条約を結んだが、その後に来たイギリスのエルギン卿は易々と同じ条約に調印出来た。しかしハリスが原案を作り、1858年に日本と調印した条約には、重大欠陥がある。確かにどちらか一国の要求で1872年に条約改定が出来る事になってはいたが、通常の条約には挿入すべきはずの条約有効期限が設定されていない。これは後で改定されない限り、いわば永久条約なのだが、当然力の強い国が反対すれば改定さえ出来ない。
この条約は日本には全く不利で、特に貿易額の過半数を握る最大貿易国のイギリスには多大な利益がある。こんな状況下で、イギリスは日本の条約改定要求に応じはするが、常に言い逃れをしたり無謀な逆提案をしたりして来た。日本の現状は、イギリスからの安い輸入品が溢れかえり、自国産業が壊滅状態である。アメリカ政府の費用は関税収入で賄われているし、イギリスにしても半分が関税収入で賄っている。所が日本は6%にも満たない。国家予算全体で見ても日本の関税収入は3%程度のもので、殆んどが農民からの税収入に頼っているのだ。一方のイギリスは自由貿易を唱えるが、日本からイギリスへの輸入品には輸入税をかけ、その総額は日本政府の総関税収入より大きい金額に上ると、具体的な数字を載せて説明した。
更に日本駐在イギリス公使の 「ハリー・スミス・パークスは」と実名を挙げ、パークスが日本で取ったイギリスの繁栄のため、特にその貿易利益のためだけに、「日本人種全体に向けあらゆる執念深さを持って行う、挑発と激怒と脅迫の外交」態度を厳しく非難攻撃した。例を挙げて、公的交渉の席でコップを投げつけて割り、この通り日本は粉々になるぞと脅したり、取り決めてある関税上陸地点ではなく、自国民の保護を名目の軍隊の上陸に勝手な場所を選んだり、交渉の席で政府高官の面前で拳を振り上げテーブルを叩いたりしたと書いた。また日本政府の役人がヨーロッパに行った時、その使用人がパークスを知らず、パークスの手荷物をホテルの部屋に届けるのを拒否したり、「サー」と言う敬語を使わず「ミスター・パークス」と呼んだという理由で、その使用人を解雇するよう抗議を受けたというエピソードまでも挙げているほどだ。パークスへ向けた厳しい個人攻撃である。
また治外法権に言及し、上述したように、治外法権を最初に日米修好通商条約に盛り込んだ張本人である、当時の日本駐在アメリカ総領事でニューヨーク在住のタウンゼント・ハリスにも書簡を送り、ハリスがその返事としてハウスに回答した、「当時のマーシー国務長官と会談したが、治外法権なしに東洋諸国との条約締結は出来ないと言われた」という書簡の文章も引用している。治外法権の設定は、アメリカ政府の指示だったと指摘したのだ。
そしてハウスは、日本はこんな多くの困難の下で文明国の賞賛を得ようと努力し、一方ならぬ成功も得つつある。こんな日本の苦しみの経験と逆境への勇敢な取り組みが、先進国の同情と寛容さを引き出せるかは明言できないが、自分は単に世間の誤った議論を修正し反転させ、日本の発展の為に闇に隠れた真実を披瀝したおきたいのだ。これによって公正な読者の目を開ければ満足である。そうなれば、必ずや正義が行われるだろうと結んでいる。
ところで、この「アトランティック・マンスリー」誌に掲載されたハウスの論文がイギリス国内で大きな反響を巻き起こし、メディアを介した一大論争にまで発展した。ハウスがパリから大隈重信宛に送った1881年6月13日付けの書簡に、ハウスのこの論文がきっかけとなり、ロンドンの「パル・マル・ガゼット」紙(The Pall Mall Gazette、ペル・メル・ガゼット又はポール・モール・ガゼットとも)上で活発な議論が起こった。また「タイムス」紙上ではリード卿 (筆者注:「日本:その歴史、伝統、宗教」の著者)とパークス自身の論争になり、パークスが弁解の投書までした。更に自分も「パル・マル・ガゼット」紙に投稿したと報告している。そして自分の感触では、パークス公使の解任は明白だ、とも報告している。実際にパークスは、この2年後の1883(明治16)年7月、日本公使から清国公使に転出しているのだ。
当時横浜で発行されていた1881年7月27日付け 「ジャパン・ガゼット」紙の1面にも、このロンドンの「タイムス」紙や「パル・マル・ガゼット」紙に掲載された日本に於けるハリー・パークス公使の行為に関する記事を見て、パークスの外交方針に従ってきた横浜居住者の間に、強い怒りの感情が広がったと報じている。そして、1年前まで横浜でハウスが発行していた 「東京タイムス」紙に触れていわく、
ここ横浜では、ハウスと云う男が4年間に渡りイギリスの方針とその外交官へ向けた敵意に満ちた記事を書き続けたのだが、役人達はそんな記事が載る新聞を購読し世界中に発送したのだから、サー・ハリー・パークスは、雇われアメリカ人から出て来る意図的に書かれた一連の中傷記事に、もっと注意して居れば良かったと残念に思う気持ちが有る。
こう書いて、完全自由貿易を掲げ、日本の政策的な輸入関税を容認しないイギリスの外交方針に何度も噛み付いたハウスの 「東京タイムス」紙に注意すべきだった、と評論したのだった。
勿論ハウスに対するこんな非難も在ったが、アトランティック・マンスリー誌に掲載したハウス論文による 「日本は公正に扱われていない」という論点に対し、イギリスのメディア上でこんな一大論争を演出できたハウスは、心底満足したであろう。また「エドワード・ハウスの欧米向けキャンペーン」で上述した井上外務卿が英国駐在の森公使に宛てた書翰で言うように、これが経緯となり、パークス公使の日本での態度が改まり、更に日本公使から清国公使に転出する遠因になったように見える。
(「The Martyrdom of an Empire」: The Atlantic Monthly、 Volume 0047、Issue 283 (May 1881)、 [pp. 610-623]、Author: House, E. H.。
パリからのハウスの大隈重信宛書簡:早稲田大学・古典籍総合データベース、大隈関係文書、英国公使パークス排斥ニ関スル書翰、請求記号:イ14 a4414。)
♦ 『日本の苦役、(The Thraldom of Japan)』 − 12カ国条約改正会議とその挫折 (1887年12月)
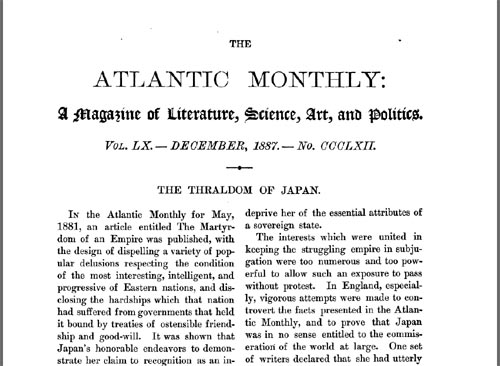 The Atlantic Monthly, Vol. 60, Issue 362 (December 1887)
Image credit: Courtesy of Cornell University Library
The Atlantic Monthly, Vol. 60, Issue 362 (December 1887)
Image credit: Courtesy of Cornell University Library
安政5年6月19日、即ち1858年7月29日に締結した日米修好通商条約以来、引き続きヨーロッパ諸国と結んだ同様の条約は、その後何十年にも渡り日本を苦しめて来た状況は、本サイトの各所で折に触れ記述している。これは、当初から挿入された治外法権による主権侵害や、その後の慶応2(1866)年5月13日、老中・水野忠精が「江戸協約」とも呼ばれる新しい「改税約書十二カ条及び運上目録」に調印し、貿易関税率を低くせざるを得ず、その後、この条約の一部として組み込まれた税率の変更はままならなかった。これがそのまま明治政府に引き継がれ、この不公平な条約を改正・修正しようとする明治政府を陰で支えようと行動するエドワード・ハウスの論文の一つが、直ぐ上に載せた「帝国の苦難」であった。そしてその6年半後に、またこの「日本の苦役」と題する論文が書かれたのだ。この論文もまた同じ月刊誌「アトランティック・マンスリー」の12月号に載り、今度は第1ページからの掲載だった。
ハウスはまず、殊にイギリスで、駐日公使・パークスをも巻き込み多くの議論を引き起こした前回の論文から書き始めている。いわく、「この最も興味深く、英知に満ち、進化を遂げる東洋諸国の状況に関する各種一般的な錯覚を一掃する事と、見せ掛けの友好と親切を規定した条約で拘束する諸外国政府に苦しめられるそんな国の苦難を明らかにする事を目論み、アトランティック・マンスリー誌の1881年5月号に「帝国の苦難」と題する一文が掲載された。過去20年間に渡り、同情と親切を受けるに値した国へ向けた連合行動で、徐々に攻撃的な敵愾心が形成され、ヨーロッパ諸国やアメリカの外交官達の意識的な妨害で、一個の独立文明国としての認知の立証に向けた日本の名誉ある努力が、失敗に帰した事が明らかにされた」。こう書き出して、その結果議論が起こり、駐日イギリス公使(筆者注:ハリー・パークス)は暫くして他国へ転出した、とその結末に触れた。この出来事は、ハウスの最も顕著な成功例だっただろう。そして日本が困憊しているのは、その改定出来ない名目5%という低い関税率と治外法権である。そして論文は再び、タウンゼント・ハリスが条約の有効期限を規定しなかったという「失敗」を繰り返し指摘した後、続けて日本の現状、即ち日本を訪問したグラント将軍も確認した如く、良く整備された陸軍や海軍、確立された海運業、成功裏に帰した教育制度、発展する鉄道網、整備が続く灯台、精密な貨幣製造技術、整備される電信網や郵便制度、国内法の整備や犯罪の少なさを述べた。この様に日本の進歩を反証として掲げ、それにも拘らず、稚拙な裁判官で行われる領事裁判の有効性に強い疑問を呈した。
続いて、1886(明治19)年5月から伊藤内閣の外務大臣・井上馨の主導で始まった、治外法権や関税率是正の12カ国条約改正会議について述べた。しかしその結末は、「深く危機感を抱く人々よる勤勉な努力で会議は1887年夏(筆者注:1887年7月29日)まで続けられたが、最後に日本は疲れ切って意気阻喪し、再度の敗北を認めた。必然的結末だった。今までかって行使されたり適用された事の無いある力が彼らに影響しない限り、ヨーロッパの競争相手は連合し、改定に合意する積りも無かったしまた合意もしないだろう」。更にハウスは1878年にアメリカと調印されたいわゆる「吉田・エヴァーツ条約」にふれ、ヨーロッパ諸国は同じ条件を受け入れず幻の条約になってしまったことを書いた。そして、「日本に対しアメリカ政府はいつも耳触りの良いことを言うが、その希望を破壊する。・・・事実、合衆国は決定的な一歩を踏み出して日本の自立と独立を支援しようとはしなかった。昨夏まで長々と続いた条約会議でも我公使は、日本に尽力するような顔色さえも見せないよう注意深く自制していた」と書いて、自国の態度を嘆いた。そして、「強国といえどもその隣国に確固とした友好で向き合う義務があるとしたら、それは日本に関する合衆国の義務である。我々(米国)が日本を平安で全体としては非常に幸福だった鎖国から引っ張り出し、国際的な興奮状態の渦に巻き込み、再々殆どその渦に飲み込まれそうになったのだ。それは、彼(筆者注:タウンゼント・ハリス)が愛した日本の永続する屈辱が分かっていれば、自らの手を切り落としもしたであろう程気位の高かった最初のアメリカ公使の言語上の大失策だったが、日本に多大な困難が降りかかって来た。そしてその後、我々(米国)の側から、彼(ハリス)の不注意な手抜かりによる不幸な条項の救済策として、どんな手も打たなかった事が誠に残念だ」と書いた。
更にその他の手段も頻りに議論され、日本政府の法律顧問を務めたぺシャイン・スミス(米人)も推奨した事があるが、万事休するまでは、と日本の政治家はその手段を採用しなかったが、それは、期日を限って条約破棄をする事であった、と書いている。平和的に条約を破棄するには、内地の全面的な解放や刑法・商法等法律上の西欧文化との等価性が無ければ諸条約国の同意は困難で、当時の国内状況では成功は無い。強いて実行すれば戦争も起ころうから、明治維新を断行した勇気と決断力のあった明治政府首脳も、ここまで築いてきた国家とその外交関係を、「条約破棄」という強硬手段による一大危機に陥れる路線は避けたのだ。筆者には、当時としては隠忍自重の末の判断だったと映る。
ハウスは、再びこの12カ国条約改正会議の結末に戻り記述を進めた。当時の歴史が示す通り、井上馨の決断した外国人の内地雑居や、判事選定と国内の法律改正条件に向けた譲歩で、関税率や治外法権条項改定がほぼ合意に至った。しかし、これを知った日本政府法律顧問のボアソナード(仏人)の反対意見をはじめ、絶対反対を唱える農商務大臣・谷干城の辞表提出など、国内の反対意見が沸騰した。ハウスの記述いわく、「政府内意見の不一致が避けられなくなった。政府内の意見調整方針を信頼できないと一大臣(谷)が辞職し、この行動で生じた大衆感情がこの政治家(井上伯爵)の辞任を求め最高潮に達した。この政治家はそう公表されて過去7年に渡り、ファビアン戦略(筆者注:共和政ローマのファビウス・マクシムス将軍の持久戦略)を取り、敵の侵攻以前に退却するという戦術で条約改正に奮闘していたのだが」。この様に井上馨が辞職に追い込まれた経緯を語り、この辞任は、日本政府を精神的に主導する一人を失った事になり、普通の遺憾の意の表明だけでは表しきれない程の重大事だ。しかし、「国内は明確に(井上の進めた方向とは)反対方向に動き、勇断をもって進めねばならない事情を良く知っていると思わる、閣外にいる人気ある指導者へ大臣就任の要請が出された。噂では、英知の幅や現実的な聡明さ、また充分な才略において井上と張り合える一人の日本人政治家に取って代わられるという。大臣として大隈重信と言う名前が出れば直ちに、長期に渡り犠牲になって来た権利と独立が速やかに主張されよう」。この様に、大隈重信に大きな期待を寄せて論を結んでいる。
ハウスのこの論文 「日本の苦役」は、外務大臣・井上馨の辞任の3ヵ月後にアトランティック・マンスリー誌に載ったが、その原稿は辞任直後に書かれたものだろう。その中で、この井上馨の辞任について 「普通の遺憾の意の表明だけでは表しきれない」と書き、ハウスは本当に残念だった様だ。この時ハウスが日本政府から支給されていた年間2,500円という年金は、上述の如く井上馨の発議で決定したものだから、その恩義の気持ちもあっただろう。しかしそれ以上に、若しこれが実現すれば、外国籍判事や検事を任用する事などかなりの譲歩があったにしろ、長年苦しんだ治外法権を日本の裁判所に取り戻し、貿易関税率も2倍を超える率になるわけだったから、それまでハウスが苦心し懸命に取り組んできた方向に一歩、二歩と近付く筈だった。それが、直前に破綻してしまったのだ。
しかし残念ながらその後の歴史が示すように、次の外務大臣・大隈重信も国内意見の強硬な反対に遭い、更に遭難もし、その他様々な日本国内の葛藤の末、イギリスとの新しい日英通商航海条約の調印は1894(明治27)年7月16日、アメリカとの新しい日米通商航海条約の調印は同年11月22日、批准書交換は更に1895(明治28)年3月21日まで待たねばならなかった。しかし治外法権は回復するものの、関税自主権の回復は不十分で、更なる交渉が必要になって行く。
(「The Thraldom of Japan」:The Atlantic Monthly、Volume 0060、Issue 362 (December 1887)、[pp. 721-734]、Author: House, E. H.)
エドワード・ハウスの永眠
♦ エドワード・ハウスの墓碑銘
 大龍寺境内のエドワード・H・ハウスの墓石
大龍寺境内のエドワード・H・ハウスの墓石
(東京都北区田端4丁目18−4、
同境内には正岡子規の墓もある。)
Image credit:© 筆者撮影
明治政府からその功績を顕彰され勳二等瑞宝章を下賜されたエドワード・H・ハウスは、その日、明治34(1901)年12月18日永い眠りについた。養女にしていた琴に看取られ、その66歳の生涯を日本で終えたのだ。筆者はこれまで3回に渡りハウスの活動を調べ書いて来たが、その生涯は誠にユニークなものだ。明治初期には多くのアメリカ人が日本に来て、各方面でその名前が知られている学者や技術者は多い。しかしジャーナリストとして来日後、これ程熱心に、長期に渡り日本の教育と外交に貢献した人物はハウスだけだろう。
このハウスの墓碑銘は養女・青木琴(後に黒田姓)に依り書かれ、右写真の墓石の裏面と右側面に刻まれている。下記は筆者がカタカナ部分をひらがなに置き換え、旧仮名遣いを新仮名遣いに直し、句読点をつけてあるが、いわく、
エドワルド、ハワルド、ハウス翁は西暦一千八百三十六年十月五日米國ボストン府に生る。齢十六歳にして操觚(そうこ、=文筆)の業に従い、往て戰地に臨み兵火を冒して通信し、還りて健筆を揮いて諤々時事を論議せり。後英佛諸國に遊び廣く政治文學美術等の諸名士と交り、又深く心を演劇に寄せ自脚本を著せり。明治二年始て我國に來り。大學南校に聘せられて教鞭を執れり。同七年臺灣の軍起る翁亦之に従い、征討記一巻を著す。其他畢生(ひっせい、=終生)文學的著作極て多し。又當時我國権の未伸揚せざるを忡(うれえ、=憂え)、或は米國の新誌を藉り或は自東京タイムスを刊行し盛に正義公道を主張し、以て我國の利益を囘護(かいご、=弁護)せり。同十二年(筆者注:十三年か)米國に帰りて下之関事件償金返還の輿論を喚起し、有力なる政治家等に説きて其賛同を得たり。同二十六年再我國に来る。翌年日清戦争起る。翁欧米諸國をして、同情を表せしめんことを努めたり。後宿痾漸加り多く病褥(びょうじょく、=病床)に在りと雖、時に我國運の消長に關する問題に對しては、克く誠に克く悃(まごころ)に堅鋭の筆鋒を以て各國の人民に告誡し、特に條約改正の為には陰に陽に其力を盡したること大なり。翁資性(しせい、=天性)樂を好み能く自奏彈し、又作曲に巧なり。晩年宮内省雅樂部及明治音樂會の為に指導誘掖する所少からざりき。かくて荏苒(じんぜん、=そのまま歳月が過ぎ)、明治三十四年十二月十七日に及びて病特に篤し。翌十八日勲二等に叙せられ瑞寶章を賜る。同日午後一時逝去す。享年六十六。不肖遺言を奉じて宗儀に依らず、亡骸を荼毘に付し、謹みて遺骨を東京田端村大龍寺の墓地に納む。是翁が生前自指定せる所なり。靈よ庶幾(こいねが)わくは、永く殊愛の地に在らんことを。
明治三十五年十二月十七日 翁の愛育を辱せる黒田琴女、泣血再拝して之を記す。
養女・青木琴については、ハウス自身の著作「Yone Santo : A Child of Japan」のモデルと聞くが、この墓碑銘から推察すれば、晩年のハウスを実の父親のように面倒を見た人のようだ。葬儀は明治34(1901)年12月21日、青山の葬儀場で墓碑銘にある如く、音楽を中心に無宗教で行われた。(The Japan Weekly Mail, December 28, 1901)
(ハウスの墓碑銘:ハウス翁墓域、「墓碑史蹟研究. 第6巻」、磯ケ谷紫江著、後苑荘出版、昭和2年10月。)
♦ 音楽を好んだエドワード・ハウス
養女・青木琴が書いた上述のエドワード・ハウスの墓碑銘の後半に、「翁資性(しせい、=天性)樂を好み能く自奏彈し、又作曲に巧なり。晩年宮内省雅樂部及明治音樂會の為に指導誘掖する所少からざりき。」と出て来る如く、ハウスは文筆のみならず音楽の才能にも恵まれていたのだ。当時のエドワード・ハウスを記述した 「Appletons' cyclopedia of American biography (1887) (アメリカ人伝記事典・1887年)」によれば、
父親・ティモシー・ハウスの息子、エドワード・ハワード・ハウスは諸学分野を自ら学び、1850年から1853年に掛けては音楽を学び、この時期に作曲した軽交響楽曲作品がボストンで演奏された。
との記述がある。ピアノは子供の頃から母親仕込みだったと聞くから、それなりの素養と実力があったのだ。碑銘文の如く自ら 「奏彈」もし、「作曲」も得意であり、「宮内省雅樂部」や「明治音樂会」の洋楽指導も出来たのだろう。当時の宮内省雅楽部は、伝統的な雅楽のみならず洋楽も演奏した(「明治30年の宮内省式部職雅楽部」、塚原康子、東京芸術大学音楽学部紀要、2005)から、ドイツ人音楽教師のフランツ・エッケルトの指導以外に、あるいは明治32(1899)年3月で雇用満期になったエッケルトの代わりに、ハウスもその指導に一役買ったのだろう。明治音楽会について筆者は良く知らないが、大正12年8月号の「思想」に載った寺田寅彦の「二十四年前」という随筆に、
その頃(筆者注:明治32年頃)音楽会と云えば、音楽学校の卒業式の演奏会が唯一の呼び物になったがこれは自分等には入場の自由が得られなかった。その他には明治音楽会というのがあって、この方は切符を買ってはいる事が出来た。半分は管弦楽を主とした洋楽で他の半分は邦楽であった。
と出て来る。この明治音楽会は、あるいは宮内省雅楽部なども演奏メンバーであったのかも知れず、エドワード・ハウスによる管弦楽の指導があったのだろう。
明治時代を通じ日本国内には実に多様な近代化の動きがあったわけだが、大隈重信や井上馨、また小村寿太郎という著名な人物と深く関わり、不平等条約の修正に努める明治政府を何とか助けようと、これ程貢献し活躍した人物の名前が、日本の歴史の中で全く埋もれているように感じた。良く知られている ウィリアム・グリフィス、デイヴィッド・モルレー、ホーレス・ケプロン、ウィリアム・クラーク、エドワード・モース、アーネスト・フェノロサ等の人物に比べ、同じ頃からその後もはるかに長く日本の教育と外交に関わった人物、エドワード・H・ハウスの名前は殆ど聞かない。日本外交史の中で、更に深く研究されるべき人物であろう。参照できた「早稲田大学・古典籍総合データベース、大隈関係文書」に感謝したい。